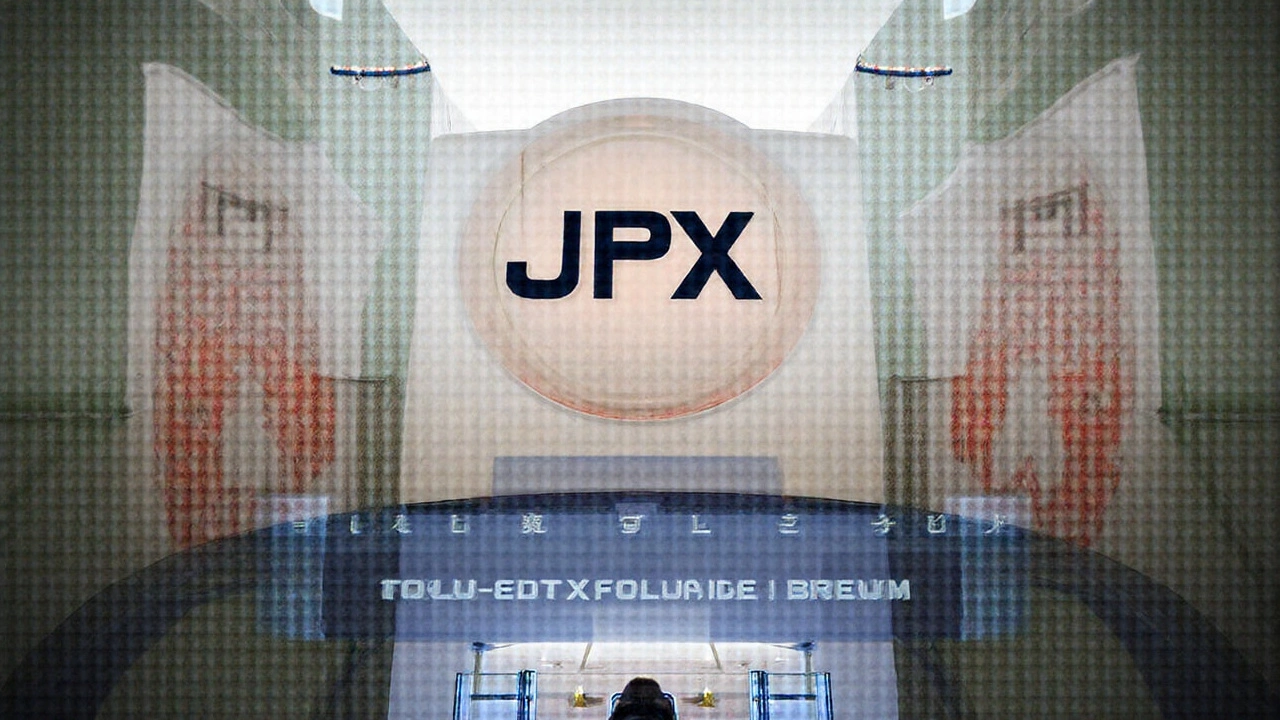4万5000円の壁は思ったより脆かった。東京市場は敬老の日の祝日明けとなる9月16日、日経平均が取引時間中に4万5055.38円まで上昇し、史上初めて4万5000円台に乗せた。前週金曜の史上最高値(4万4888.02円)をあっさり上回り、2カ月足らずで8回目、9月だけで4回目の最高値更新だ。節目を意識した売りをこなしつつ、ザラ場で何度も4万5000円を出入りする強い値動きが続いた。
背景には、米株とくにAI関連を中心とした大型ハイテク株の上昇がある。前夜の米市場で投資家のリスク選好が戻ると、東京でも半導体製造装置や電子部品といった「グロース×輸出」色の強い銘柄に資金が流入。指数は値がさウエートが大きいだけに、時価総額の大きいテック株が素直に全体を押し上げた。
タイミングも良かった。米連邦準備制度理事会(FRB)の政策スタンスに対する「タカ派の頂点は過ぎた」との見方が根強く、利下げ時期はなお流動的ながら、長期的に金利は低下方向に向かうとの期待がリスク資産の追い風になっている。金利の天井観測はハイテク株に効きやすく、それが東京にも波及した格好だ。
国内要因も強い。円安で輸出採算が改善し、電子・自動車・機械などの業績見通しは上方修正の余地が意識されている。東京証券取引所が求める資本効率改善の流れは24年以降も定着し、自社株買い・増配の発表が常態化。新NISA導入で個人マネーの流入も続き、海外投資家の需給改善と相まって、株式市場の「下支え」が分厚くなった。
そもそも日経平均は、株価の「水準」が高い銘柄ほど指数への寄与が大きい価格加重型だ。半導体製造装置など一部のハイテク大型が上がると、指数は想定以上に押し上げられやすい。米AI投資の波に日本の装置・材料・部品が連動し、指数に強力な上げ圧力がかかる構図は、今年に入ってから何度も確認されてきた。
何が市場を押し上げたのか
第一に、米ハイテク株高。生成AI向けデータセンター投資はサイクル初期の色合いが強く、日本の装置・計測・材料の受注を押し上げている。とくにメモリ投資の回復や先端ロジックの歩留まり向上に関連する工程は日本企業の強みが多く、東京市場のキープレイヤーが米ナスダックの地合いに連動しやすい。
第二に、金利観測。FRBの引き締めが「長期化はするが、強度は弱まる」との読みが広がると、リスク資産全般に資金が戻りやすい。米長期金利の振れは依然大きいものの、投資家は「次の一手が利下げ方向に傾く」可能性を織り込みはじめ、株式に資金を寄せる流れが続いている。
第三に、国内の構造要因。東証によるPBR1倍割れ企業への改善要請を受け、還元姿勢の強化や事業ポートフォリオの見直しが広がった。ROEとガバナンスの改善は海外勢の評価を引き上げ、需給面でも買いが入る。賃上げの定着で内需の底上げが期待される一方、円安は輸出採算と外貨建て収益の円換算を押し上げる。複数の追い風が同時に効いている。
短期の需給も無視できない。祝日を挟み、海外の上昇を後追いする「ギャップアップ」になりやすい地合いだった。節目の更新が続いたことでトレンド・フォローの資金も加速し、先物主導で指数が押し上げられる場面も目立った。
一方で、指数の上昇が広範に及んだかというと、値上がりの寄与は半導体・電機など値がさに偏る。恩恵が指数に先行して現れるのはいつものパターンで、相場の持続には裾野の広がりが必要になる。
相場の持続性とリスク
足元の最大のリスクは、米テックの反落だ。AI関連の成長ストーリーは強いが、金利・需給要因で短期的な調整は避けられない。日本の装置・部材セクターは感応度が高く、米市場のボラティリティが跳ね上がると東京も巻き込まれやすい。
日銀の政策も要監視だ。賃金と物価の好循環が進むほど、緩和の「度合い」を調整する局面は増える。もし国内金利がじわりと上がり、同時に円高方向に振れれば、輸出主導の業績見通しにブレーキがかかる可能性がある。とはいえ、他国と比べれば金融環境は依然として緩い。市場は「正常化は進むが、急がない」と読むが、サプライズは常にリスクとして残る。
バリュエーション面では、一部の成長株でコロナ後のレンジ上限に近づく水準が見られる。期待値が先行すれば、業績の上振れが続かない限り、株価の滞空時間は長くない。とくに指数寄与が大きい銘柄ほど、決算やガイダンスの一言で相場全体の温度が変わる。
海外マクロも不確実だ。米景気の減速度合い、中国の不動産・消費の回復の鈍さ、供給制約や地政学の揺れは、企業の投資・生産計画に影を落としうる。足元のエネルギー価格や物流コストの再上昇も、利益率の計算を難しくする。
当面のチェックポイントは、今週予定される米FOMCのメッセージ、国内では日銀会合のスタンス、そして主要企業の中間期見通しだ。増配や自社株買いの追加発表が続けば、需給面の支えは厚くなる。逆に、為替が急反転して円高が進む、あるいは米テックに調整が入るなら、4万5000円の上での滞在は長くない可能性がある。
最後に基本に立ち返る。日経平均は225銘柄で構成されるが、価格加重ゆえに「高い株価の銘柄」が指数を動かしやすい。指数の上昇と自分のポートフォリオの体感がズレるのはこのためだ。相場全体の方向感を見るには有用だが、投資判断ではTOPIXや業種別、個別の業績トレンドとあわせて確認したい。
4万5000円の初到達は、単なる通過点か、それとも節目として意識されるのか。外国人の買い越しが続き、企業の稼ぐ力が伴うなら、次の高値探しは十分あり得る。目先はイベントリスクをこなしつつ、業績の「本物度」を見極める時間帯に入る。